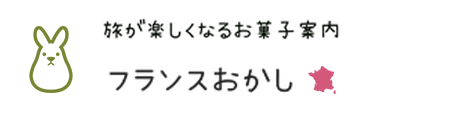現在、ガレットデロワは1月6日のエピファニーの祝日に食べられます。
そもそもエピファニーってなんなのでしょうか。そして、なぜこの日にガレットデロワを食べるようになった伝統ができたのでしょうか。
エピファニーとは?
エピファニー Épiphanie はとは1月6日のキリスト教の祝日です。(祝日ではありますが休日とはなっていません)
日本では主顕節や公現節とも呼ばれます。
聖書によると、3人の博士が東方で巨大な赤い星を見つけました。それは救世主の生まれたしるしであるという言い伝えにより、彼らはラクダに乗って星を追い続けました。
すると、12日目の1月6日にベツヘルムの馬小屋の真上で星はとまりました。3人の博士はイエス・キリストの誕生にまみえ、黄金・乳香・没薬を贈りものとしてささげました。これにより主の誕生が人々に知られることになりました。
それが1月6日です。
ガレットデロワがエピファニーに食べられるようになるまで
現在ではガレットデロアはエピファニーに食べられていますが、昔はガレットデロアは宗教的な祭りとは関係がないお菓子でした。
そもそもガレットとは円形に薄く焼いた生地のことで、新石器時代には穀粉と水や乳などで溶き、熱した石の上にのせて焼いたのが始まりでした。蜂蜜などで甘味をつけて甘い生地としても食べられていました。ガレット・デ・ロワとは「王様のガレット」「王様のお菓子」という意味です。
ガレット・デ・ロワは古代ローマ時代にはサトゥルナル Saturnales の祭りの際に供されていました。サトゥルナルとは豊作と繁栄の神であるサトゥルヌ Saturne を祝う祭りのことで、ローマ暦で12月17日から12月23日まで行われていました。

サトゥルナル Saturnales の祭りの様子
[ 画像引用:https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois ]
祭りの間には王を決めるための選挙を行っていました。投票の方法はくじ引きで、そら豆をひいた人が王様になるという習わしです。
後にキリスト教が広まったとき、この習慣が主顕節でのお祝いでのお菓子にも引き継がれていきました。そら豆はキリストを表していました。
お祝いの食べものに使うということで、キリスト教徒はこの習わしを意図的に認めて、キリスト教の普及に一役買っていました。
中世時代に、ガレットデロアは太陽と太陽の光のシンボルとなっていました。教会が先導してエピファニー(主顕祭)を祝うためにガレットデロアを食べていました。
11世紀にはブザンソンの教会で教会の責任者を決めるためにパンの中に硬貨を隠しました。この習慣は他の教会にも広まっていきました。その後、銀貨は小さな豆に代わりました。
13世紀に入ると、王の祭りのときにフェーブのお菓子が売られていました。そのお菓子は次第に家庭でも作られるようになっていきました。
17世紀に入ると、そら豆をキリストに見立てるという考え方が冒涜的だとして陶器の人形に変えられました。

その後フランス革命をきっかけにガレットデロワの製作はパティシエやブーランジェといった職人たちの手に渡っていきました。
現在ではガレットデロワをエピファニーの日に食べますが、宗教的な意味はなくなり、お菓子やイベントを楽しむようになっています。